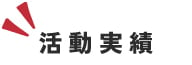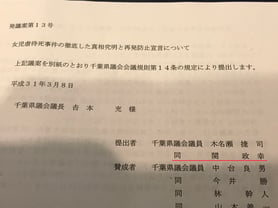多種多様の個性は無限の可能性!
『為せば成る、為さねば成らぬ何事も。成らぬは人の為さぬなりけり。』
自分だったらどうする?
5年後の私たちの街、どうなってる?
考える、そして実行する。みんなも、私も。
そんな地域政治を一緒につくっていきませんか?

7月30日、TOKYO MXテレビ「堀潤激論サミット」『低い使用率・・・AEDの理解を深めるには?』に出演しました。
冒頭、隣の髭男爵・山田ルイ53世さんからの大きな「ルネッサ~ンス」。
「びっくりするや、ないか~い。」とワイングラス片手に切り返したかったところでした・・・が・・・そんな余裕はありませんでした。笑。
AED推進について、千葉県では、条例制定から約8年となり、AEDの設置や講習等のトレーニング機会の増加など進んでいると認識をしていますが、一方で、使用率は5%程度の推移で横ばいです。
また、使用が必要とされる状態(心原性心停止の状態)の人の数は、本県で、一日あたり約3人から、1日あたり約4人へと、高齢化によって増加傾向となっています。
119番通報からの救急隊の到着時間も、高齢化による出動件数の増加とパラレルに延びている傾向にあります。
科学的・データ的根拠から飛躍的な生存率と社会復帰率に繋がっているAEDは、「命を救う社会インフラの一つ」として改めて大切だと思いました。
・・・「訴訟リスク」から女性への使用に後ろ向きな意見が見られることについてどうか?」・・・
そのリスクは極めて低いです。
訴訟リスクは基本的になく、弁護士として受任するようなケースは、極めて限られると思います。
一方で、たしかに、例えば、状況的に恥ずかしい姿を大衆の場で曝け出されたことを理由とする損害賠償請求(精神的損害など)など、理論上は民事の訴訟提起は可能です(本人による訴訟提起など)。
しかし、万が一、訴訟提起されたとしても、通常の心肺蘇生法の実施とAEDの使用であれば、裁判所において、民法の緊急事務管理(698条)の適用や要救助者の合理的意思や違法性の解釈等で請求が認められる可能性はまずないと考えます。
特段の悪質な事情があれば別でしょうが、普通は、弁護士をつけるなどしてきちんと応訴すれば上記結論に至ります。
この点を踏まえて、千葉県の条例では、応訴のための弁護士費用の貸付などの援助規定を設けました(13条)。
そして、ここの貸付は、訴訟結果を受けて、返還が「免除」されますので(14条)、救助実施者に負担が生じないようになっています。
勇気を出して行動に出てくれた救助実施者に、万全のサポートをするために備えたものです。
あくまで万が一のためです。実際のところ、条例の制定から約8年たちますが、この弁護士費用の貸付例はありません。
裏を返せば、訴訟リスクが極めて低いことを、この8年が示しているともいえます。
一方で、この援助規定の利用例として、救助実施者が返り血を受けたことによる感染症検査のための費用援助のケースがあります。
ところで、今回の番組出演にあたり、上記に関する判例を調べていた中で、逆の意味の裁判例を見つけました。
つまり、AEDの使用をしなかったこと、救助実施をしなかったことを理由に訴えられたケースとなります。
東京地方裁判所令和4年4月25日判決は、ゴルフ場のプレー中に心停止の状態となり最終的に亡くなってしまった方の遺族等が、ゴルフ場や従業員に損害賠償請求をした事案です。
要点だけ説明しますと、救急車が到着するまでの間に、場内に設置していたAEDの使用や心肺蘇生法の実施が可能だったのに怠ったという旨の原告の主張に対し、ゴルフ場側の安全配慮義務の内容や当日の事実関係などが争われました。
原告の請求は棄却されましたが、AEDの普及が広がり、いざという時に当然のように使用される世の中になれば、むしろ、実施しなかったことによる訴訟リスクが生じることを示唆するものとも言えます。
特に法的義務が生じるような関係性があればそれは高くなると思います。
・・・「いざという場面で、ためらわずに行動できるためには・・・?」・・・
各コメンテーターからは、「日々の手伝いや社会貢献の積み重ねが大事」、「ドナーカードのように、何かあったら実施して欲しいと予め表記しておく」など・・・新鮮な発想でとても参考になりました。
私自身も、もし現場に直面したら、不安で一歩を踏み出す勇気が絶対に必要になると思っています。
それをアンパンマンのマーチで乗り越えようと、自分に言い聞かせ、あらかじめ心構えをしています。
とにかく、要救助者の命が優先されるので、躊躇なく実施をしていただきたいです。
「命を救う社会インフラの一つ」として、更なる普及に努めてまいります。