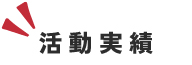多種多様の個性は無限の可能性!
『為せば成る、為さねば成らぬ何事も。成らぬは人の為さぬなりけり。』
自分だったらどうする?
5年後の私たちの街、どうなってる?
考える、そして実行する。みんなも、私も。
そんな地域政治を一緒につくっていきませんか?

本日(4月4日)、ちば自民党政調会では、新型コロナウイルス対策の中でも、感染爆発に備えた医療体制の整備に絞って、現段階で把握できた県当局の取組み状況の確認と、先手が必要なポイントや後押しを強化すべき事項を中心に議論を行いました。
その詳細を下記に整理しましたが、確認できていない事項を含めて、県当局の対応を求めてまいります。
この背景には、先の台風災害での経験則から、危機管理としての先を見据えた対応が苦手かもしれないとの疑念を受けて、万全を期すべきと考えたからであります。
特に、欧米を中心とする一気に感染者が増えたことによる医療崩壊の惨事が発生している例を教訓に、一刻も早く最悪の状態をも視野に入れた準備を進めなければなりません。
人類未経験のウイルスへの流動的な対応が求められている中で、危機管理で、我々議員のような、切り口の違う視点を持った側からも、重畳的な検討を加えていくことは大事だと思っております。
まず前提として、3月14日に施行された新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「法」とします)を受けた政府対策本部決定の「新型コロナウィルス感染症対策の基本的対処方針」(3月28日付)及び党本部政務調査会決定の「緊急経済対策第三弾への提言」(3月31日付)を踏まえ、法31条に基づく医療等の実施の要請等を、緊急事態宣言の発令(法32条)、オーバシュート、更にその先の状況をも視野に入れています。
また、法は、既存の「千葉県新型インフルエンザ等行動計画」を今回の行動計画とみなしますので(法附則第1条3項)、この行動計画と、それを受けた「千葉県新型インフルエンザ等対応マニュアル」を参考としています(以下で、それぞれ単に「行動計画」、「対応マニュアル」とします)。
記
○千葉県の医療資源の状況とキャパシティーについて
先日の投稿と重複する部分は簡潔にします。
現在、対応病床の増加が急務となっていますが、計画では、現在の247病床から、段階的に400床、850床(移行期)、1700床(蔓延期)と、フェーズに応じて増やすこととなっています。
そのためには、対応可能な病院と医療従事者等の確保を急がなければなりませんが、県当局は、4月1日に病院関係者への説明会を実施したところです。
更に、対応マニュアルでは、「県は、感染期以降は、全ての医療従事者が新型インフルエンザ等の診療に従事することを想定し、研修・訓練を実施する。」(90頁)としており、研修や訓練の実施に向けた準備も必要です。
治療に欠かせない人工呼吸器の県内保有数は417台、人工心肺(ECOM)では29台でありますが、それらの増台とそれを扱えるスタッフの迅速な確保・育成が必要となります。国の増産が待たれるところですが、ある私立病院では、器機を有していながらも、マスク等の資材不足を原因に稼働ができない事態があったようですので、資材の分配についても、きめ細やかに行き届くように差配する必要あります。
限られた病床や医療機器の利用状況に関する情報等の集約・把握・共有が肝要ですが、これを患者に差配する部署で利用することができる体制(システム)の構築については、国でシステムの提供と関係病院への呼びかけ中とのことですが、その進捗が分かりません。
千葉の場合は近隣都県との連携により相互に受け入れ合い支えあう仕組みが必要ですが、上記の医療整備の進捗に併行して実施されるべきです。
病床以外における軽症患者や無症状者に対応施設の確保や在宅療養の支援体制の整備も必要となるところですが(法48条、行動計画、対応マニュアル90頁)、昨日、東京で大手民間ホテルによる施設提供の協力の報道がありました。これには敬意と感謝の念がつきません。
さらに、病床が追いつかない場合には、いわゆる野営病院の準備も必要となりますが、これらのスタッフについては、「県医師会等と連携し、臨時の医療施設においても医療を提供するために医療関係者を確保し、必要な医療を提供する。」(対応マニュアル90頁)ことになっていますが、そのための段取りがどのようになっているのか気になるところです。
そして、感染拡大の抑制のために、PCR検査強化の実施が求められていますが、上述した受入体制の整備の進捗に併せて拡大を図っていかなければなりません。
今回は、感染力を考慮し、感染期に入った段階においても、帰国者・接触者対応外来・センターを通じた差配ルールを原則とする形を当面は継続するようです。
○現場医療従事者へのサポート体制の強化について
感染拡大の混乱時に備えた、必要な医療器機・資材、サポートスタッフを補充できる仕組みを構築する必要があります。これは、法55条の物資の売り渡し要請や収用の運用準備を含めてです。
感染症対応に必須となるPPEなどについては、行動計画で、「県及び保健所設置市は、国と連携し、医療機関の従業員の勤務状況及び医療資器材・医療品の在庫状況を確認し、新型インフルエンザ等やその疾患に係る診療が継続されるよう、国、県医師会、医療機関等と調整する」(健康福祉部・50頁)とされています。
また、海外で見られるように、長期の職場滞在を余儀なくされる事態を想定した医療従事者への環境支援も必要です。地域や病院ごとに状況が異なることが想定されるので、こういった現場の声を拾い上げる仕組みと体制(ホットライン)を作っておくべきでありますが、現状は、担当課が窓口に位置づけられるとのことです。
特に感染が拡大して混乱状態に入った際には、各病院等へのサポートが迅速に出来るように整理しておかなければなりません。医療従事者に生じる負傷や罹患などについては、政令で定めるところにより損害補償が定められています(法63条)。さらに、従事することへのインセンティブについては、他国で基金から支出している例を踏まえた検討もされているようです。
自衛隊による支援については、基本的には、最終手段に近い段階での検討となるようです。
○県当局について
現段階で対応にあたる県関係部署は、対策本部を筆頭に、健康福祉政策課、疾病対策課、薬務課、医療整備課、健康福祉指導課・・・保健所・・・等多岐に及びます(対応マニュアル15頁)。
現場対応に追われていることは明らかですので、実働部隊へのサポートが必要で、総務部でニーズを整理しながら来週以降で人員補充の対応を行っていくようです。
そして、これは非常に大事なことだと思っていますが、議会側としては、県当局のプランの全容や具体的な段取りと現在の位置状況が見えてきません。どこまでを想定し、準備を進め、今はどの段階で、いつまでに各事項の完了を目途としているのか、全体の状況把握とその進捗管理が説明できる人員がいないのではないかと懸念しています。前記してきた事項への回答状況から懸念するものですが、この点は、司令塔の事務局にあたる人員と併せて補充すべきです。
○情報提供について
行動計画では、情報提供・共有の目的を「・・・各々が役割を認識し、十分な情報を基に、適切な行動をとることが重要である。そのため、対策の全ての段階、分野において、国、県、市町村、医療機関、事業者、個人間でのコミュニケーションは双方向性のものであり、一方方向性の情報提供だけではなく、情報共有や情報野受取手の反応の把握までも含むことに留意する。」(14頁)としています。
医療体制の整備状況・計画とその進捗状況や見込みを県民にきちんと示し、それを共有することが、県民との危機意識の共有にも繋がり、県民の協力に訴える自粛要請に説得力を持たすことになります。
また、感染者情報については、現状の本県の運用では、基本的に保健所設置者単位となっていますが、町村単位まで細かく発信するべきです。
以上のような議論でしたが、中には進められていて、徒労に終わるものがあるかもしれません。
でも、それはそれでよいことで、二重のチェックになればよしです。
また、当局において準備をしすぎて、結果的に空振りに終わったとしても、今回は許されるべきです。
そして個人的には、今いろいろと議論となっている学校の再開は、この医療体制の整備の進捗状況を踏まえて、感染爆発への十分な体制が担保された段階で行われるべきだと思っています。
こちらの視点からの先を見据えた取り組みを、細かいものを含めて提案してまいります。
感染が拡大して混乱状態に入ったら手遅れですので。
我々議員側で出来ること、毎朝の検温による最低限の体調把握や、議会棟での入庁管理の徹底化も確認しました。
今日の会議についても、3密を避けるために、十分な席の距離の確保と配置の工夫や換気を徹底しました。
最後になりますが、
コロナに打ち克つぞ!がんばろう日本!!